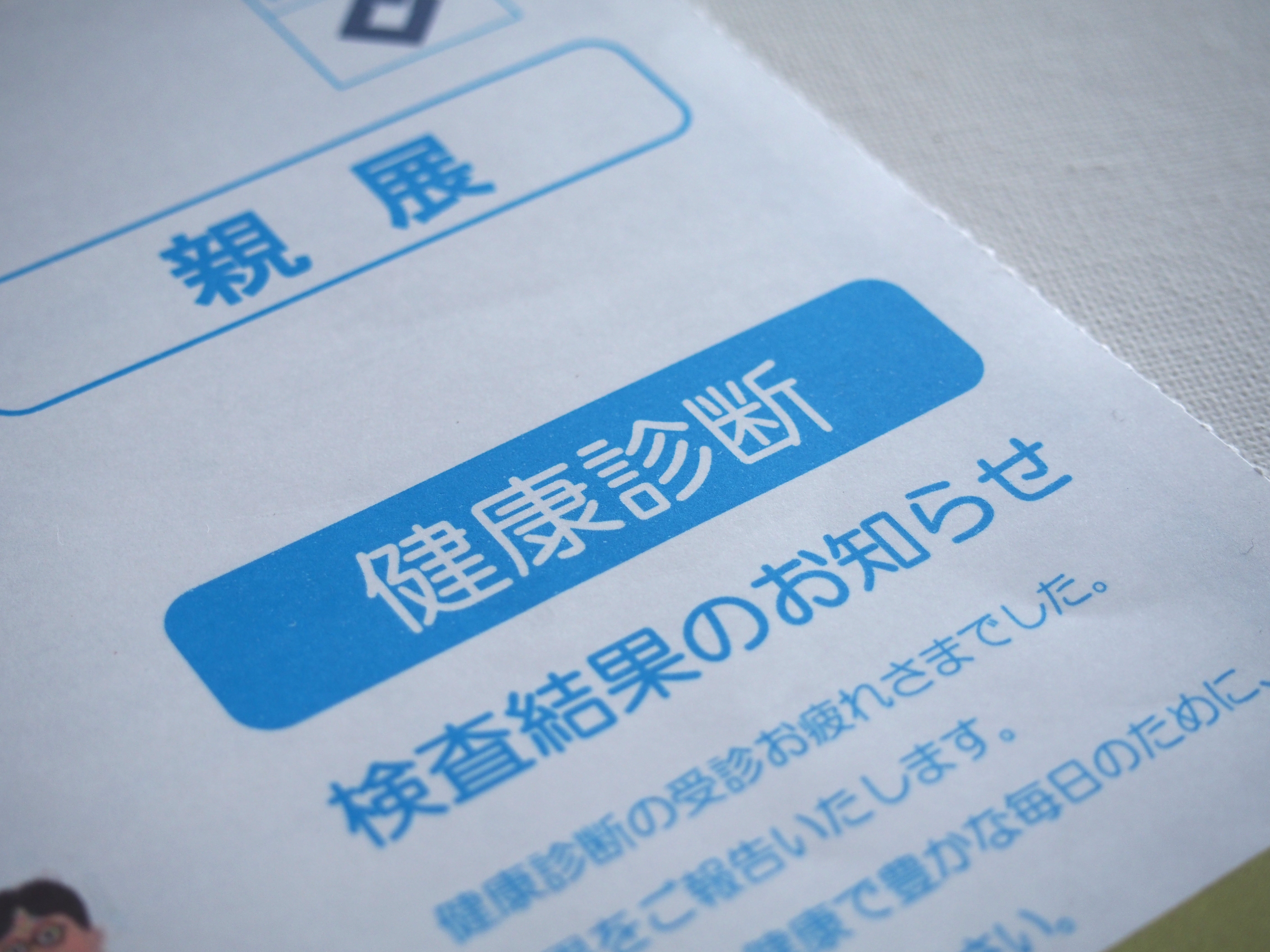- コラムタイトル
-
保険は健康なうちに加入するのが基本! その3つの理由とは
- リード
-
病気やケガによって入院せざるを得ない状況に備えて、「保険」に加入したほうがよいのではないかと思いつつ、後回しにしていませんか。保険商品や保険会社はさまざまあるため、どれを選んだらよいのかよく分からないし、保険ショップに行くと、押し売りされそうな気がするなどの理由で、結局何もできていないのが現状かもしれません。
将来の健康のリスクに備えるためには、健康であるうちに保険の加入を検討することが重要な意味を持ちます。その3つの理由について、詳しく解説していきます。
- コラムサマリ
★この記事は約5分で読めます。
・人生100年時代、加齢とともに高まる病気のリスクへの備えが重要。
・保険の基本は、健康なうちに加入すること。
・自分の健康を過信せず、後悔のないようにリスクに備えたい。
- 本文
-
保険は将来が不安な人が入るものと思っていませんか?
将来の健康リスクに対して、前もって備える方法のひとつが「保険」です。特に20代で健康な人にとっては、病気や感染症による入院や闘病、死というものをイメージしにくいかもしれません。ただし、不安がないからといって、何も対策をしておかないと、想定外のリスクに見舞われ、生活が脅かされる恐れがあります。
今や人生100年時代といわれ、100歳を超える人が身近にも増えていると思います。一般的に、加齢とともに病気になる可能性は高くなります。病気の治療や通院にはお金がかかりますし、病気によっては就業できない状況になる場合もあります。実際には、傷病手当金によって会社を休んだ場合の収入の保障、高額療養費制度によって高額な医療費の負担の軽減ができるものの、自己負担額は少なくありません。
健康であれば保険は不要、病気になったときのために貯蓄があれば保険は不要、という意見もあります。考え方として誤りではありません。ただし、貯金は必要な金額まで増やすのに時間がかかるものです。途中で病気になった場合は、貯金を中断することになる恐れがあります。
一方で、保険に加入した場合は、治療費の負担を抑えられるため、経済的な心配を抑えつつ治療に専念できる可能性が高まります。
保険は健康なうちに加入するのが基本
いずれにしても、健康なうちに、早い段階で対策をすることが大切です。では、なぜ健康なうちに保険の加入を検討したいのか、以下の3つの理由を挙げてみます。
理由1:病気になってからでは加入できないこともある
そもそも、保険とは、一人ひとりが少しずつお金を出し合い、困っている人にお金を渡すという「相互扶助」で成り立っています。いつ、誰が困った状況になるか分からないため、万一に備えた、支え合いのシステムになっています。そのためには、「公平性」が必要です。
闘病中や持病があることで給付金を受け取る確率の高い人が加入すると、不公平が生じます。そのため、保険の加入には自分の健康状態などを生命保険会社に伝える必要があります。
理由2:加入できても一部が不担保となる場合も
不担保とは、各保険商品の基準に適合していない場合に、保険に加入していても所定の期間、保障されない(保険金が支払われない)ことです。現在治療中の病気やケガ、既往歴などから、特定の病気や特定部位についての保障を「不担保」とする条件がつくこともあります。
理由3:加入できても保険料が高い商品しか選べないことも
持病があっても、保険料を増額することで加入できる保険商品もあります。また、通常の医療保険よりも診査項目の少ない「引受基準緩和型」の保険も販売されています。ただし、これらの保険商品は病気などがあっても保険に加入できることから、保険料の負担は大きくなります。
自分が健康であることへの思い込みも危険!
男性に比べ、女性は貧血になりやすいです。貧血は血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンという物質が少ない状態のことですが、このヘモグロビンの量が低下すると、眩暈(めまい)や動機・息切れ、月経異常などのさまざまな不調を引き起こすため、軽視してはいけません。
貧血を起こしやすい要因として、過度なダイエットや偏食などがあります。また、、赤ちゃんに栄養を与えることで、自分自身が栄養不足となりがちな妊娠から授乳期、さらには更年期障害なども貧血になりやすいため、女性にとっては生涯にわたって貧血のリスクがともなうことを知っておきましょう。
病気になってから後悔しないようにしたい
現時点で健康で日常生活に不安がない場合は、病気によって生活に支障が出るイメージができず、保険の加入については後回しになりがちです。病気になってから「保険に入っておけばよかった」と後悔しないようにしたいものです。
まずは、キャリアや結婚、子育てなどの人生計画(ライフプラン)を考え、その時々で病気やケガによって生活に支障が出た場合にどうなるのかを想像してみてください。そうすることで、保険があることによって得られる恩恵をリアルに考えられるでしょう。
この記事の執筆協力
- 執筆者名
-
大竹麻佐子
- 執筆者プロフィール
-
証券会社、銀行、保険会社など金融機関での勤務を経て独立。相談・執筆・講師活動を展開。ひとりでも多くの人に、お金と向き合うことで、より豊かに自分らしく生きてほしい。ファイナンシャルプランナー(CFP©)ほか、相続診断士、整理収納アドバイザーとして、知識だけでない、さまざまな観点からのアドバイスとサポートが好評。2児の母。ゆめプランニング URL:https://fp-yumeplan.com/
- 募集文書管理番号